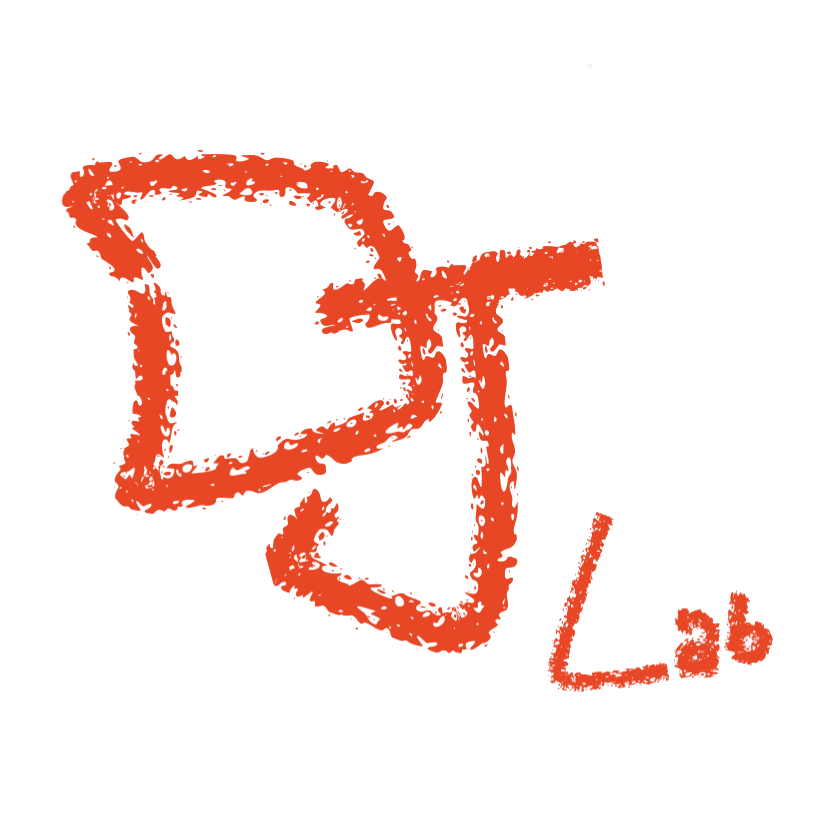2021 etm team B
代表挨拶
日本は少子高齢化による労働力の減少、過疎地域のさらなる過疎化・高齢化が進んでいます。特に「ものを運ぶ」ということに関して、この問題は顕著にあらわれています。そうした現状への対応としてロボットによる自動化を行い、より暮らしやすい環境を作りたいと考えております。
所属員紹介
- 代表 井上裕貴
- リーダー 湯浅聡太
- メンバー 川野智博
PJ概略
離島での自動配送ロボットの運用
自動配送ロボットを用いて離島での配送を無人化する。
進捗状況
離島(北九州市藍島)での配送事情の現状調査
要素
・過疎地域での配送ロボットの利用
集荷所に一度集められた定期便の郵便物の仕分けまでを島の方に担当してもらい,輸送を配送ロボットで代替する.
・配達サービスを地域に適応させるための調整
ロボット側の調整を行い,ロボットのシステム・通信方式などを,導入する過疎地域の通信環境に合わせる必要がある.
海外製のロボットを導入する場合、ロボットのシステムをローカライズする必要がある.
地域側の道路に線などを引くことができれば,倉庫や工場などのライントレースが可能な搬送ロボットも使用可能となる.
・配送ロボットの資金
現在販売されているデリバリーロボットを購入し,地域向けに改良を加える.
初期費用500万円で月額10万円より安く,ロボットを提供できるように廉価なロボットを購入し,使用することを想定
北九州市では,ロボット産業の振興に3.2億円,定住・移住促進事業に3千5百万円の予算を当てているので, そこから開発費などを得ることができるのか検討する.
・配送ロボットの安全性
人や障害物と接触しないか,衛生的に運搬できるかといった問題が考えられる.そこで,すでに実証実験が行われているロボットを用い,ある程度の安全性や収納の密閉性が担保でき,安全な走行ができることが考えられる.
・ロボット運用のための法律・規則
実証実験のための道路使用許可を得るためには、ハードウェア面では身体障害者用車いすと同じ基準を満たしている必要があるため、その基準を満たすようなロボットを調達する必要がある.
ただし,歩道を走る自動運搬ロボットは、現状では法律で定義されておらず、法改正が必要.ハードウェア面では,身体障碍者用車いすと同等以上の規則が,ソフト面では自動運転の規則を統合した新たな規則がそれぞれ設けられればロボットの運用が容易になるのではないか.