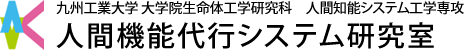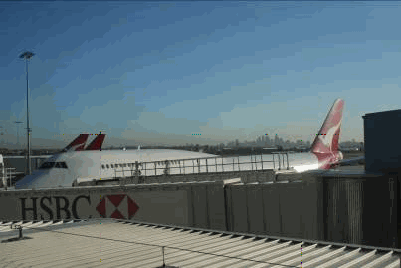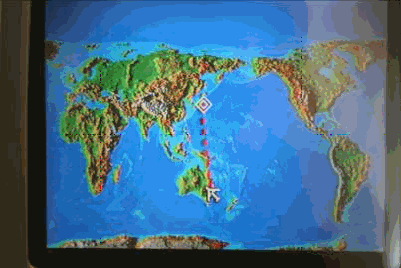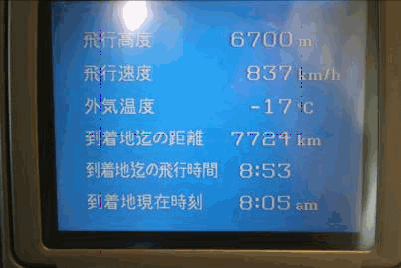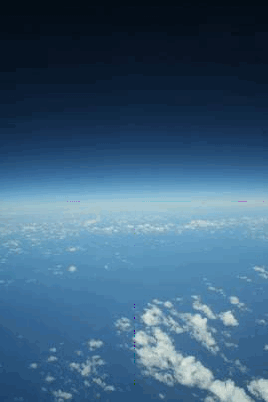シドニー通信 最終号 2009年3月23日 和田親宗
8ヶ月あまりの滞在を終え、3月19日夜12時前に北九州の自宅に戻りました。可能ならもっと長く滞在したかったと言うのが、正直な感想です。と言うのは、8ヶ月だと研究をするにも中途半端な期間ですし、英語力を伸ばすにも中途半端、遠隔地からの学生指導も中途半端、と全て中途半端に終わってしまったような気がするからです。もちろん、私の低い時間管理能力のせいでもありますが、0から始めた研究の場合、何らかの成果を出すには2年は必要と思っているからです。
滞在中に移動手段に関し気づいたことをいくつか記します。シドニーのタクシーには大きく分けて4種類の車種があります。セダンタイプ、ワゴンタイプ、ミニバンタイプ、大型バンタイプの4つです。セダンとワゴンが多く、次にミニバンがよく見る車種です。これら3つは街中に流しとしても走っており誰でも気軽に乗れます。大型バンは9人乗り程度の大きな車で、一般的には予約制です。セダン、ワゴン、ミニバンと三種類走っていますので、例えばトランクを二つ持っている場合にはセダンではなくワゴンを選ぶことができますし、大人数の場合ミニバンを選ぶこともでき、多様な選択ができます。それも予約なしで可能で、とても便利です。日本ではそのあたりに走っているタクシーでワゴンタイプやミニバンタイプを見たことがありません。また、ミニバン、といっても全てがトヨタのエスティマで車いすが後部から乗り込めるようになっています。この車が街中を走っているのです。と言うことは、車いすで街中に出かけたとしても、辺りに走っているエスティマに乗れば時間に縛られることなく予約も必要なく自由に移動できることになります。一種のバリアフリーと言っても良いかもしれません。ごくたまに、車いす専用のタクシーも見かけます。あまり見かけませんので、おそらく予約制ではないかと思います。このタイプの車も見たことがありません。シドニーの歩道はガタガタで車いす使用者にとっては歩きにくいように思います。もちろん、スロープは整備されていますので歩けないことはありません。ただ、車いすが歩道を移動しているのを見るのは希ですので、おそらくタクシーやバスでデパートなどの目的地まで移動し、目的地周辺を車いすで移動する方略を採っているのではないかと思います。
街中のタクシー、セダンタイプとワゴンタイプ
車いす乗降可能なミニバンタイプタクシー。後部バンパー付近からスロープが出てくる
これは帰国時に頼んだ大型バンタイプのタクシー
車いすリフトが内蔵されており、トランクの積み卸しに利用していた
車いす専用のタクシー、後部にスロープが内蔵されている
バリアフリーの点から考えると、バスについては、日本より良い部分もあります。町中に走っているバスの内、感覚的には半分以上が低床式のノンステップバスです。北九州市営バスのものと似ています。違う点は、車いす(あるいはベビーカー)用のスペースが確保されていることと、車体傾斜装置がついていることです。車いすあるいはベビーカー用のスペースには、簡易椅子が三つついており、車いす等がない場合にはその椅子に座ることができます。しかし、ベビーカーなどが乗ってきた場合には、その椅子を跳ね上げスペースを作ることになります。このスペースにベビーカーを置くと、通路の通行の邪魔になりません。よく考えられていると思います。車いすの場合には少し通行の邪魔になる可能性はありますが、完全に塞ぐことにはならないでしょう。車体傾斜装置は、おどろくほど傾きます。車いすやベビーカーが乗り込もうとすると運転手が車体を傾かせ、ステップの高さをかなり低くします。これはとても良いと思います。以前慶応大学の湘南キャンパスに行ったときに乗ったバスも車体傾斜装置がついていました。日本製のバスではなかったような記憶があります。このように日本にも導入されていますが、残念ながら私の知っている範囲では、北九州で見かけません。車体傾斜装置付きの低床式ノンステップバスは、車いすやベビーカー使用者だけでなく、足の悪い人にとっても乗り降りしやすいものですので、積極的に導入して欲しいと思います。
低床式のノンステップバス
 後ろから車内後方を見る
後ろから車内後方を見る
(右上方が運転席)
前から車内前方を見る
(後方に行くには階段を登る)
車いす用スペース
(赤いシート三つを跳ね上げる)
もう一つ、ある種のバリアフリーを紹介します。信号機です。シドニーの信号機には歩行者用押しボタンがついています。全てとは言いませんが、ほとんどの信号機についています。押しボタンを押さないと歩行者用信号は青になりません。青にならないと基本的には歩行者は横断できません。車は横断者がいないと言う前提のもと、猛スピードで走りますので、信号無視で横断する際には要注意となります。この押しボタンスイッチから常に音が出ています。赤信号の時には1秒周期程度でカッツ、カッツ、カッツ、青信号になると0.5秒周期程度でカッ、カッ、カッ、という感じです。音とあわせて、押しボタン本体も同じ周期で振動しています。日本のように大きな音でないことと高音でないことから、交通量の大きな場所では聞こえない可能性はありますが、日本のようにうるさくなることもありません。一般的な傾向として、交通量の大きな場所は人通りも多いでしょうから、仮に音が聞こえなくても周囲の誰かが助けるであろうことを前提にしているのかもしれません。日本の音響信号の設置は、公共施設や視覚障害者用施設の周辺などの場所に限られています。しかし、シドニーではほとんどの信号が音響信号機です。タクシーやバス、音響信号機の状況から、シドニーでは障害者が自分自身で行動するための最低限のインフラが整っているように思えます。まず自分で行動し、もし困ったら誰かに助けてもらう(あるいは周囲の誰かが自然に助ける)という行動原則なのかもしれません。日本では、行動したくてもその方法がない場合が多いことと比較すると、障害者支援に対する考えが根本から異なっているように思います。
信号機の押しボタンスイッチ
横断歩道と押しボタンスイッチ
以下は帰国時の写真です。
シドニー空港から、カンタス航空ボーイング747とシティ中心部
遠くにあるのが、シンガポール航空のA380(総二階建て航空機)
シドニー空港、成田行きJAL搭乗口
シドニー出発
ほぼまっすぐ北へ
30分経過時点、残り約9時間、この時日本は朝8時過ぎ
機内食、シラーズ(オーストラリア産ワイン)とともに洋食をいただく
天気が悪くゴールドコーストは見えず、ただ一度珊瑚礁を見ることができた
飛行高度が高いためか、空が黒い
軽食のサンドイッチ
あと少しで日本到着
謝辞
滞在中、UTSでは、次の皆様にお世話になりました。写真を載せるとともに感謝の意を表したいと思います。
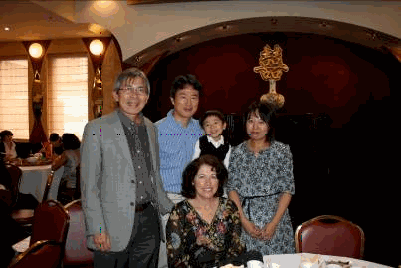
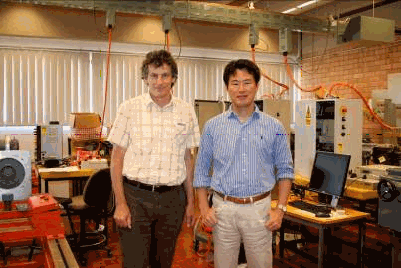
Professor Hung Nguyen and Lesley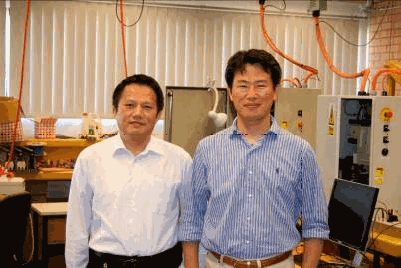
Dr. Greg Hunter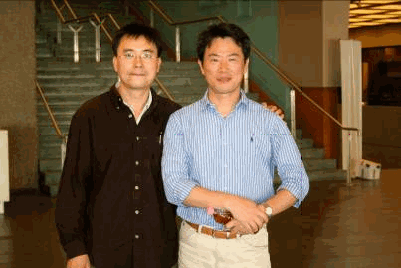
Lecturer Youguang Guo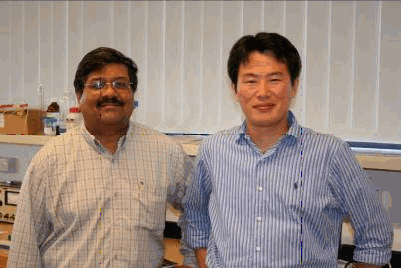
Associate Professor Ananda Sanagavarapu